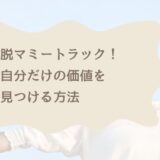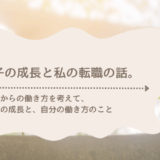「そろそろ別々に寝た方がいいのかな…?」
小学校高学年の男の子を育てていると、そんなふうに感じる瞬間が増えてきますよね。
まだ多少幼いけれど、なんとなくツンッとした感じも出てきたり、会話が減ったり。
“心と体の成長のサイン”が見え始めたときこそ、親としての距離の取り方に迷いますよね。
この記事では、母子の「一緒に寝る」時期の目安と、
離れるときに意識したい“心の準備”を、私の実体験を交えてまとめました。
焦らず、無理せず、親子のペースで進めていけるように。
うちでは、小6の中学受験が終わった冬に、別々に寝始めました。
なんとなく「そろそろかな」と思っていた頃に、
息子が突然、「今日はひとりで寝る」と言い出して。
いつもはリビングからつながる息子の部屋に、
二人分の布団を並べて敷いていたのですが、
その日、私は別の部屋に布団を持っていって寝ました。
なんとなく寂しかったけれど、「あぁ、こんな感じなんだな」と思ったのを覚えています。
(ちなみに我が家、夫のいびきが殺人的レベルのため、夫だけ別室です…笑)
中学受験の頃は、やっぱり不安定な時期だったのか、
「ひとりで寝る」なんて言うことは一度もありませんでした。
だからこそ、心の成長とともに自然とその時期が来るんだなと感じます。
周りのママの話を聞いても、
中学生に上がるタイミングで完全に個室にした、という家庭は多い印象です。
やっぱりタイミングは人それぞれ。
でも、“自然にその日が来る”ことを信じて待つのも、ひとつの見守り方だと思います。
心の成長とともに変わる“物理的なあり方”
これを境に、心の距離感も少しずつ変わってきた印象があります。
中学生になると、一気に友だちとの関係が深まっていきますよね。
うちの子は運動部に入ったこともあり、学校生活の比重がぐっと大きくなりました。
そのせいか、親との関係もそれまでとは少し違うものに。
なんでもあけすけに話してくれていた時期から、
どこか一歩引いたような、“客観的な関係”に変わっていった気がします。
「まあ、困ったら相談してくるでしょ」くらいのスタンスで構えていないと、
つい心配しすぎて疲れてしまう——それが正直な実感です。
うちの子は同級生の中でも少し幼いタイプで、
中学受験もどちらかといえば“やらされ感”が強めでした。
その反動なのか、中1になりたての頃はゲーム三昧。
自分で勉強する習慣が身についておらず、親としては少し焦りました。
そこで私が取り組んだのが、「勉強の仕組み化」。
具体的には、「中1男子なんて放っておいても何もやらない!」と割り切り、プロに委ねる。
個別塾を週2回、学校の復習専用で組み込みました。
部活で忙しいのは承知のうえで、自宅から3分の個別塾に“強制送還”。
この仕組みを回し始めたことで、夏休みにはようやく学習習慣が定着。
あとは、もう「野となれ山となれ」精神で見守るだけです。
それでも、ときどき少し元気がないときや、
父親に生活習慣のことで怒られたあとなど、
なぜか私の寝ている部屋に来て、横で寝ることがあります。
それを見ていると、
「まだ心の中では甘えたい部分があるんだな」と感じる瞬間もあって。
それもまた、成長の途中にある“心の揺れ”なのかもしれません。
私はそのときだけは、何も言わず“ナスがまま”にしています。
自然と、ゆっくり自立していく
中1の夏ごろ、声変わりが始まりました。
同級生たちもすっかり“男子”っぽくなってきて、
女の子に比べてのんびりしている男子のだらしなさに、
ついヤキモキしてしまうこともあります。
でも、見ていないようでちゃんと成長しているものですね。
ある日、中間試験の真っ只中の夜に、
突然「部屋のレイアウトを変える」と言い出した我が子。
少し前に買ったすのこベッドとマットレスを動かして、
突っ張り棒式のカーテンで仕切りをつくり、
自分だけの空間をつくりあげました。
「今それやる!?」と思いつつも、
なんだか誇らしく感じました。
“自分でこうしたい”が、どんどん増えてきたんです。
完全な個室空間を実現したその日、
ああ、こうして少しずつ**「自分の世界」を整えていくんだな**と感じました。
自立って、ある日突然起こるものじゃなくて、
こういう小さな「自分で決める」の積み重ねなのかもしれません。
親が“離れ方”で意識したい3つのこと
子どもがだんだん自分の世界を持ち始めると、
うれしいような、ちょっと寂しいような、なんとも言えない気持ちになりますよね。
「部屋こもって何してんの?」
「スマホばっか見てない?」
…って言いたいけど、言えばムッとされる。
そんな時期を、どうやって“穏やかに”乗り切るか。
私が試してみてよかった3つをまとめてみました。
正直、口出したくてたまらない瞬間、あります。
テスト勉強中にマンガ読んでたり、机の上がカオスだったり…。
「ちょっとは片づけなよ!」って言いたくなるけど、言えばケンカになるだけ。
だから私は、物理的に距離を取る作戦を決行してます。
・部屋から出て、とりあえず外を歩く
・スーパーに逃げる(無駄に野菜を眺める)
・それでもモヤモヤしたら、サウナで整える
・そして最終手段は、ChatGPTにぶちまける(笑)
これ、けっこう効きます。
文字にして吐き出すと、だんだん冷静になって、
「まあ今日じゃなくてもいいか」って思えるんですよね。
自立してきたとはいえ、やっぱり子どもって、
ふとしたときに頼ってくるもの。
ただ、こっちが焦ってアドバイスを始めると、逆効果。
だから私は、助言よりも“聞く”にシフトしました。
「そうだったんだ〜」「へぇ〜」「それでどうしたの?」
これだけでだいたい話が落ち着きます。
アドバイスを求められたときだけ一言添えるくらいがちょうどいい。
“何も言わない勇気”って、実はけっこう効果的です。
一緒に寝なくなっても、
反抗的な態度を取られても、
親子の絆はちゃんと残ってる。
むしろ、少し離れた今の方が、
「自分の世界を持ちながら、信頼でつながってる」感じがします。
たまに夜、寝てる私の横に来てゴロンとすることもあって、
「あ、今日は疲れた日だったんだな」ってわかる。
それで十分。
離れるって、“終わり”じゃなくて、“信頼のはじまり”なのかもしれません。
勉強のことは、プロに全ベット。
中学生になって思ったのは——
「親が勉強を管理しようなんて、もはや無理」ってこと。
放っておくとマジでやばい。
でも、こっちが口出すと関係がギクシャクする。
なので我が家は、思い切ってプロに丸投げしました。
個別の先生に“全ベット”。
うちは、中1男子の自己管理能力を信用しない戦略です(笑)
とはいえ、丸投げしっぱなしにはしません。
「何をどう任せるか」だけは、ちゃんと親が握る。
たとえば、
・学校のカリキュラムの流れ
・長期休みのスケジュール
・家庭でのペース(部活との両立など)
この“外枠”を親が把握して、
その中で先生に目標設定を子どもと一緒にやってもらうようにしています。
結果、親は“仕組み担当”、先生は“実行担当”、子どもは“当事者”。
役割分担ができると、家庭がほんとに平和になります。
ただご予算もあるので、英数以外はスタディサプリをやってもらってます。
朝登校前に、なんとなくやる習慣がついてます、いつまで続くかわからんけども。
まとめ:離れても、ちゃんと見守ってる
思春期の親子って、距離をとることがゴールじゃなくて、
それぞれの場所でちゃんと生きてることを認め合う時間なんだと思います。
「自分でやりたい」が増えた息子。
「もう全部背負わなくていい」と気づいた私。
夜に一緒に寝なくなって、
部屋にカーテンをつけて、
勉強をプロに任せて——
それでも、心はちゃんとつながってる。と信じてる…笑
晴れた朝みたいに、
「大丈夫、ちゃんと育ってる」って思える日が増えました。
そして私も少しずつ、“母”をアップデート中です🌿
▶ 男の子って、いつまで一緒に寝ていいの?まだ一緒に寝てるけど…というママへ
息子の成長をきっかけに、私自身の働き方も見直すようになりました。
今までは“キャリアを抑える”選択をしてきたけれど、
子どもが自分の世界を持ち始めた今こそ、
私も「これからの自分」を整えるタイミングかもしれないなと感じています。